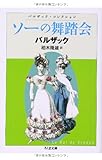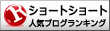東電OL事件 - DNAが暴いた闇
「崎義一の優雅なる生活 BLUE ROSE」
・崎義一の優雅なる生活 BLUE ROSE/ごとうしのぶ 角川書店
今から1年前。 あんな納得のいかない終わり方をしたタクミくんシリーズ。 その、まさかの続編。 私をBL(あの頃はまだそういう言葉なく、耽美とかJUNEものだった)という世界に嵌らせてくれた、タクミくんシリーズ。 とても大切な作品。 正直、続きが出た嬉しさと、今更なぜ出るのかという呆れとがあった。 それでも、やっぱり読みたくて、雨が降ってウォーキングができない夜(買ったその日)に読んだ。 書き下ろしの表題作と、書き下ろしのバレンタインデーの話と、雑誌に掲載された短編を加筆修正したもの。 私は雑誌を読んではないので、どれも初読み。 あれから、11年後。 ギイがニューヨークにあるクラブで友人と話をしていシーンから、始まる。 会話の中に、恋人の託生のことが出てくる。 はぁ? いつの間に、もとさやに? どうなってんの? 一方のタクミくんは、大学で井上教授の助手をしている。 井上教授って、あの井上佐智くん?! いつのまに、教授になったんだ? しかも、タクミくんのことを教えていたなんて、よーわからん。 ギイが仕事をリタイヤし、ニューヨークからタクミくんのいる日本に来た。 二人、高校の時のように、ごく当たり前に会話している。 表題作は、井上教授のもとに贈られたバイオリンの謎を解く話。 うん、こういうの、高校時代の時にもあったね。 いつものタクミくんシリーズというわけか。 でも、でも。 私が読みたかったのは、こんな話じゃなくて、突然いなくなったギイと、結局、東京の音大に通うことになったタクミくんが、どうやって再会しまた恋人同志になったのかと言うこと。 話の最後にちょこっとだけ出てくる。 それじゃよくわからないんですけれど? ふたつめの話に、二人のその後、離れ離れになっていた時のバレンタインのことが出てくる。 タクミくんが自分で一歩前へ踏み出し、ギイへチョコを送る。 別れてからギイは大学の研究室にいる、ということがわかった。 なるほどね、戻ったわけね。 ギイは前向きだったんだね。 けど、タクミくんに何か言ってからアメリカへ帰るべきだったよ。 ギイが何も言わなかったなんて、ありえないよ、ごとうさん。 3つめは、タクミくんの大学生の時の話。 最後に今に戻り、ギイがタクミと再会した時のことがちょこっと書かれている。 なんだかなぁ。 まあね、タクミくんシリーズらしいといえばそうなんだけれど、こういういつものタクミくんシリーズではなく、二人が再会する話を読みたかった。 あれから11年。 リタイヤしたギイが、タクミくんの元へ攫いに行くという話を。 ソフトカバーでイラストは付いてないんだけれど、帯に29歳のギイが描かれていた。 描いたの、おおやさんじゃないし このギイもいいけれど、おおやさんの描いた29歳のギイが、見たかった。 ★★★ シリーズの一部はこちら↓
Station 小冊子付き特装版 タクミくんシリーズ (角川ルビー文庫)
- 作者: ごとう しのぶ
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2014/01/31
- メディア: 文庫

そして春風にささやいて―タクミくんシリーズ (角川文庫―ルビー文庫)
- 作者: ごとう しのぶ
- 出版社/メーカー: 角川書店
- 発売日: 1992/04
- メディア: 文庫
今年読んだ中国語の本
中国語も少なく8冊のみ。
 『诚实律师:林肯总统的律师生涯』
『诚实律师:林肯总统的律师生涯』
布莱恩·德克(歴史家)
法律出版社(2009)
(誠実な弁護士:リンカーン大統領の弁護士生活)
アメリカのリンカーン本の中国語訳版。20年以上の弁護士時代について解説している。大統領としての能力は弁護士時代に養われたことがわかる。
(中国語多読65冊目。2014.12.29読了。)
 『离歌(1)』
『离歌(1)』
饶雪漫(作家)
万卷出版公司(2008)
(離歌(1))
(中国語多読64冊目。2014.11.01読了。)
 『明朝那些事儿(第3部):妖孽宫廷』
『明朝那些事儿(第3部):妖孽宫廷』
当年明月(明史学)
浙江人民出版社(2011)
(明朝那些事儿(第3部):魔物たちの宫廷)
(中国語多読63冊目。2014.10.12読了。)
 『明朝那些事儿(第2部):万国来朝』
『明朝那些事儿(第2部):万国来朝』
当年明月(明史学)
中国友谊出版公司(2007)
(明朝那些事儿(第2部):万国来朝』)
(中国語多読62冊目。2014.06.13読了。)
 『报刊逻辑与语言病例评析1100例』
『报刊逻辑与语言病例评析1100例』
首都师范大学出版社(2008)
(新聞雑誌の論理と文法ミスの分析1100例)
(中国語多読61冊目。2014.06.09読了。)
 |
龍應台(作家)
天下雜誌(2009) (台湾海峡一九四九) (中国語多読60冊目。2014.04.10読了。)
 『嗜血的皇冠(大结局):光武皇帝之刘秀的秀』
『嗜血的皇冠(大结局):光武皇帝之刘秀的秀』曹昇(作家)
时代文艺出版社(2011) (血塗られた王冠 結末編:光武皇帝の劉秀の秀) (中国語多読59冊目。2014.02.02読了。)
 『民族学生汉语病句修改200例』
『民族学生汉语病句修改200例』李金山
内蒙古教育出版社(2005) (民族学生漢語間違い文添削200例) (中国語多読58冊目。2014.01.14読了。)
BL小説「ロッセリーニ家の息子 継承者 上下巻」(岩本 薫)

 ロッセリーニ家の息子 継承者 (上) (角川ルビー文庫)
ロッセリーニ家の息子 継承者 (下) (角川ルビー文庫)
(作:岩本 薫/画:蓮川 愛)
【あらすじ・上巻】
ロッセリーニ家の息子 継承者 (上) (角川ルビー文庫)
ロッセリーニ家の息子 継承者 (下) (角川ルビー文庫)
(作:岩本 薫/画:蓮川 愛)
【あらすじ・上巻】
新年を迎え、シチリアのマフィア一族・ロッセリーニ家の本邸“パラッツォ・ロッセリーニ”に久々に集う三兄弟―レオナルド、エドゥアール、ルカ―とその最愛の恋人たち。数々の苦難を乗り越えて幸せを掴んだ彼らだったが、レオナルドが「秘密」をエドゥアールに打ち明けたことを発端に、兄弟の絆が揺らぎ始め…。岩本薫が贈る極上のラブ・ロマンス「ロッセリーニ家の息子」シリーズ文庫版第5弾前編。三兄弟を長年見守り続ける執事・ダンテ視点の書き下ろしを同時収録。 (角川ルビー文庫・角川書店より)
【あらすじ・下巻】
誰が何を言おうが、俺たちの仲を引き裂くことはできない―それぞれの秘密を告げ合ったロッセリーニ家の三兄弟・レオナルド、エドゥアール、ルカ。家族の絆と最愛の恋人たちとの愛情の狭間で揺れる彼らに与えられた試練、その結末とは―。岩本薫が贈る人気シリーズ「ロッセリーニ家の息子」文庫版第5弾後編。単行本収録の番外編2編に加え、ファン待望の各カップルの後日談を描いた100ページ超の大ボリューム書き下ろしを同時収録!メガヒットシリーズ、感動のクライマックス。 (角川ルビー文庫・角川書店より)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
作品お気に入り度 ★★★★★
挿絵お気に入り度 ★★★★★
感想。。。
文庫化シリーズもとうとう最終章です。(上下巻2014.11月刊行)
何度読んでもときめくシリーズなので何だか寂しいな。
上巻ではいよいよ3組6人が初顔合わせ。
そして自分達が恋仲って事を隠しているようで、偶然から一人、一人、バレていく様子が面白ドキドキです(*^^*)
そのバレ方も、一人にバレて、バレた人は気づいてなくて、その人もまた別の人のを目撃して・・・みたいな。
何かロシアンルーレットのような感じ(笑)
最後はレオの激怒で続くになった上巻。
単行本で下巻、結末(オチ)は分かっていても読むのにワクワクしてしまいます^^
書き下ろしはダンテ視点。
ダンテのロッセリーニ一族と兄弟達を思う気持ちが存分に感じられて良かったです^^
(読了日:2014.12.6)
感想下書きの間に下巻も読み終えたので一緒に感想。
シリーズ全6作、文庫版で再読、読み終えたー!!
面白かったなぁって改めて思う。
皆んな同性を愛してしまっているし、このシリーズのスピンオフも皆んな同性カップルになっていくみたいなのでありえないーって思いつつ、このありえない展開だからこそドキドキなんです(*^^*)
そして何度読んでも、本編が終わった後の彼らの恋バナ(?)のショートが面白くて(特にレオとエドゥアール!)・・・。
あぁ美しくて素敵なエドゥアール様も、このショートではすっかり“オヤジ化”(笑)
でも礼人の事になると普段の冷静さがぶっ飛ぶっていうのも“萌え”なんですけれど(^^)
そして単行本から気になっていた彼らの“もっとその後”が読めたのもすごく嬉しかった!!
生まれてくる子の性別も分かったし^^
ひとまずこれで終了って感じだけれどやっぱり寂しい。
まだまだ彼らに会っていたい~(^^)
スピンオフはサイモン編しか読んだ事ないので、これから少しずつ読んでいこうと思います!
(読了日:2014.12.11)
*****
シリーズ既読感想
・【文庫版】ロッセリーニ家の息子 共犯者
・【文庫版】ロッセリーニ家の息子 捕獲者
・【文庫版】ロッセリーニ家の息子 守護者
・【文庫版】ロッセリーニ家の息子 略奪者
2014年のベスト5
〇 2014年に私が読んだ文庫本の、ベスト5を勝手に紹介します。 この1年間の読書は、アメリカ文学に偏っていました。 ・ 第1位 「白鯨」 メルヴィル (岩浪文庫・3分冊) とてつもない小説です。今まで読んだどんな作品とも違います。 圧倒的なスケールと存在感で、文句なく今年のナンバー1です。 3月中、「白鯨」の世界に、完全に入り込んでいました。 考えさせられる作品です。まさに、人生に影響を与える作品です。 → http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-03-20 → http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-03-29 ・ 第2位 「ある婦人の肖像」 ジェイムズ (岩波文庫・3分冊) 「白鯨」と並んで、私が今年最も夢中になった作品です。 小説としての面白さでは、文句なく今年のナンバーワンです。 それなのに、岩波文庫で品切れ状態。(残念!) どうしても読みたくて、ヤフーオークションで購入しました。 → http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-06-29 → http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-07-05 ・ 第3位 「緋文字」 ホーソーン (古典新訳文庫) これまた、とても面白くて、色々と考えさせられる小説です。 ホーソーンの独特の世界に、どっぷりとはまってしまいます。 →http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-03-08 ・ 第4位 「ファウスト博士」 T・マン (岩波文庫・3分冊) 悪魔的な魅力を放つ物語で、とてもマンらしい作品です。 岩波文庫で出ていましたが、現在品切れ。新訳を切に希望します。 →http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-01-10 ・ 第5位 「セールスマンの死」 アーサー・ミラー (ハヤカワ演劇文庫) せつなくてせつなくて、思わず泣けてしまう戯曲です。 一生働き続けながら破滅してしまう父と、自分と重ねて読んでいました。 →http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-08-29 ・ その他の作品について。 遠藤周作の「深い河」「沈黙」「イエスの生涯」も印象に残っています。 →http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-10-03-1 →http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-09-25 →http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-09-11 ヘミングウェイの「武器よさらば」や「日はまた昇る」なども紹介しました。 どちらも大好きな作品ですが、初めて読んだ作品ではないので対象外です。 ちなみに、「武器よさらば」は、私の生涯ベスト5に入る作品です。 「武器よ」→http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-04-01 「日はまた」→http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2014-08-20 〇 続いて、2014年の登場人物(?)ベスト5です。 ・ 第1位 「白鯨」に出てきた白鯨。モービィディック。 「人物じゃないだろ」というツッコミはなし。文句なしの第1位。 ・ 第2位 「白鯨」のエイハブ船長。 人物に限定すれば、エイハブの存在感は圧倒的でした。 ・ 第3位 「進撃の巨人」のエレンとミカサ。 「コミックもありかよ」というツッコミはなし。カッコ良さでは1番。 ・ 第4位 「アブサロム、アブサロム!」のサトペン。 悪魔的な魅力を放つ、実にあくの強い男です。 ・ 第5位 「ファウスト博士」のアドリアン。 サトペンとは違う意味で、悪魔的な魅力を持つ人物です。 〇 ナイス文庫大賞。 2014年に出た文庫本の中で、良かったものを勝手に二つ選びました。 ・ 「情事の終り」【新訳】 グリーン (新潮文庫) →内容もすばらしい、訳もすばらしい、カバーも良い、値段も適正。 この本を724円で世に出したところに、新潮社のプライドを感じます。 文庫本はこうあるべきだ、という模範的な本。誰にでも勧められます。
・ 「バルザックコレクション(3分冊)」 バルザック (ちくま文庫) →「暗黒事件」など、文庫で読めない傑作を、まとめて出してくれた。 まだ読んでいないので、紹介はしていないが、来年絶対に読むつもり。 岩波文庫から出た「艶笑滑稽譚」にも注目。 〇 ちなみに、2013年のベスト5は・・・ →http://ike-pyon.blog.so-net.ne.jp/2013-12-29 〇 今年も、みなさんにお世話になりました。 この地味なブログを、読んでくださって、ありがとうございました。 来年もまた、よろしくお願いいたします。 2015年は、18世紀の小説を中心に読むつもりです。 また、バルザックなど、19世紀小説で新訳が出たものも読みたいです。 ホメロスなどの古典も、今度こそは読んでおきたいと思っています。 〇 さいごに。(我が家の10大ニュース) 2014年の我が家の10大ニュースの1位は、夏のキャンプです。 初めてトレーラーハウスに寝泊まりして、娘は大喜びしました。 それから、私が仕事で表彰されるという、予想外の出来事もありました。 また、4月から役職を降りました。そのおかげで、この冬は11連休です。宅配買取ドロップ
甘城ブリリアントパーク 特典クリアファイル
『コミュニティデザインの時代』

コミュニティデザインの時代 - 自分たちで「まち」をつくる (中公新書)
- 作者: 山崎 亮
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2012/09/24
- メディア: 新書
内容(「BOOK」データベースより)昨年10月、所属する学会の全国大会に出席するために訪れた広島で購入し、それから1年以上、タンスの肥やしにしてしまった本である。今年11月、出張で米国に行く際、コンパクトな新書サイズだからという理由でなんとなく携行して読みはじめ、なかなか集中できなかったけれどもなんとか読み終わった。でもそこからがさらに試練で、ブログで紹介記事を書こうと思っていたのになかなかその時間を作れず、そのうちに記憶もだんだん薄れてきて、書かれている内容を忘れていってしまった。今でもこれを紹介できるのかどうか不安ではあるが、年を越したくないので敢えてここで紹介しておく。 著者の山崎亮氏は、2012年頃から「コミュニティデザイン」と名のつく本を次々と世に出しはじめ、注目を集めはじめた時代の寵児ともいえる人だ。元々は建築デザインを大学で専攻されたようだが、時代は人口減少社会へと転じようとしていたその時期、無名のデザイナーが腕を振るえるハードの建築物の設計の機会は少なくなりつつあった。そこで新たなチャンスとばかりに見出したのが、建築物だけではなく、地域社会のあり方を地域の住民の参加も得てデザインしつつ、その中で求められる「場」としての構造物・建築物の設計をも参加型で進めるという「コミュニティデザイン」の発想だった。従って、デザイナーが自分の思い描いたデザインを形にするというのではなく、その地域に入り込んで、住民が持つニーズとリソース、そして発想などを引き出し、それらをつなぎ合わせて地域自体の設計に生かしていこうという、ファシリテーターのような役割に、建築学の専門知識がドッキングしているのがコミュニティデザイナーなのかな、僕はそう理解した。 氏が経営するデザイン会社を通じてこのコミュニティデザインを手掛ける実績を積むにつれて、国内各所において講演の依頼等が氏のところに舞い込んでくるようになった。そして、講演を行なう際に毎回同じような質問が参加者から投げかけられることに気付いた。そこで、FAQに対する整理された回答をまとめておこうということになり、この本の執筆に至ったのだという。目次の項目を見ていくと、講演会の会場でフロアからどんな質問を受けたのかが容易に想像できる。だから、最初から最後まで通して読むという読み方だけではなく、一種のレファレンスとして、必要な時に必要な箇所だけ読むという方式での読み方にも合っているかもしれない。 結果として、面白かった箇所もあったし、面白くなかった箇所もあった。節と節の間がぶつ切れになっていたり、同じケースの引用が随所に出てきたり、編集段階でもなかなか整理しきれなかったのだろうと思われる読みづらさが本書には存在する。多分それが読むのに時間がかかってしまった理由だろうし、書かれていたことを思い出すのにも難儀した理由でもあったのだろう。 ただ、幾つか自分なりには重要だと思ったポイントがあるのでここで挙げておきたい。 第1に、地方が課題先進地域であるという視点。日本が課題先進国だというのは僕らもよく用いる主張なのだが、その先進的な取組みがどこにあるかというと、超高齢化や人口減少、財政危機といった課題が最も早くから顕在化したのは地方だ。だから、地方で地域活性化を進める取組みに関わっている人々は、もっと胸を張ってそれを誇ってもいいということらしい。 第2に、著者が言っているように、コミュニティデザインには「その人と地域の特性にあったやり方がある」というのはその通りだと思うけれど、やっぱりどこの地域に行っても通用する一般化・概念化された方法論というのを提示しておかないと、日本の地方は元気にはなれないとも思う。山崎氏とそのスタッフが日本全国津津裏々までカバーされるのならともかく、実際には同様のコミュニティデザイナーがもっと沢山育ってこないと、時代の要請には応えられないのではないかという気もする。この本は地域住民のニーズに応えるというか、ニーズの掘り起こしの方をまだ狙って書かれているように思える。 第3に、そうはいっても、こうした取組みに参加してくれる地域住民というのは限られるのだなという点。ある意味、これがいちばんショックだった点でもある。本書によると、著者が関わった人口2300人の町ですらまちづくりに参加していない2000人が存在するとのことである。だいたい2割の人が参加し、残りの8割は参加していないということになる。これが一種の黄金律で仕方のないことなのか、それともやっぱり2割よりももっと増やしていく必要があるのか、著者は後者の立場を取っているように思えるが、著者自身も成功していない点であるともいえる。 ただ、発想を変えれば、山崎氏の関わるコミュニティデザインの取組みに乗る人がその程度の人数であったとしても、それはそれでいいのかもしれない。別に地域活性化の取組みを山崎氏の主宰するデザインに集約する必要もないわけで、他に別の人的ネットワークによって同様に優れた取組みでも起こっているならそれは良いことではないか。 我が街でも、人口17万人の自治体において、100人程度の住民の無作為抽出と有志の組合せにより、まちづくりの基本計画を作ったことがあったらしい。僕らはその計画が出来上がった後に転入してきているので、参加する権利自体はなかったと理解しているが、この計画策定に携わった人々は今でも強固な横のつながりがあり、それが様々な形でのまちづくりの取組みのコアとなっている様子が見受けられる。こうして様々な取組みが増殖していくこと自体は悪いことではない。でも、この強固な横のつながりは、濃密すぎて僕らのようなレイトカマーがちょっと入りづらい雰囲気も醸し出している。言い方は悪いが、「内輪で盛り上がっている」という印象もある。 まちづくりの取組みにはできれば参加したいけれど、なんとなく参加しづらい―――人をどうやって引っ張り込むか、あるいは背中を押せるか。結局のところ、コミュニティデザインがうまくいくには、そこのところをうまくやれる地元のファシリテーターが育つことが重要なのかもしれない。外部者は手を差し伸べることはできても、背中を押すようなところまで入り込むには時間もかかるのではないか。
孤立死や無縁社会という言葉が毎日口にされる現在の日本。今こそ人とのつながりを自らの手で築く必要が痛感されている。この時代の声に応え、全国で常時50以上のコミュニティづくりに携わる著者が初めて明かす、住民参加・思考型の手法と実際。「デザインしないデザイン」によって全員に参加してもらい結果を出すには?話の聴き方から服装にいたるまで、独自の理論を開陳する。ビジネスの場でも役立つ、真に実践的な書。
PR: ≪JAL国内線≫先得で早めの予約がおトク!
「TVニュースのタブー」
若松英輔「生きる哲学」を読む
2ヶ月ぐらい前、もったいない本舗から段ボール箱5枚が届いていた。思い切って本を整理しようと思ったのだった。いくつか詰め込んで、そのうち催促が来たのだがそのままになっていた。そうしているうちに「自称2062年の未来からやってきたという未来人2062氏(本名不明)の予言」というのに出会った。その中にこんなQ&Aがあった。
Q.なにか持っといた方がいいものとかあるの?
A. 書籍は大事に保管だ。
もったいない本舗さんには申し訳ないが、そんなわけでずるずるになってしまっている。そうこうしているうちに「読む」ことの意味をあらためて認識させられる本に出会った。若松英輔さんの『生きる哲学』。いろいろ忙しいのに、一気に読ませられた。人は悲しみによって形而上学の世界(根源的実在の世界)に導かれる、自分にとってそんな悲しみとは何なのか。
クライマックスとも言うべき章が、「第13章 読む 皇后と愛しみが架ける橋」だった。
柳宗悦が援用される。
《悲しみは、痛みの経験であると共に、慈しみの芽生えでもある。どうして悲しみが、悲惨なだけの経験であり得よう。「美し(かなし)」と書くように「かなしみ」の底にはいつも、無上の美が流れている。そのことを忘れた近代を、柳は憂う。悲しみは、その深みにおいて、対立の関係にあるものの姿を変え得る力をもつ。宗教における超越者は、宗派の差異を超え、悲しみの衣をまとうように存在していることに注意を促す。ここで柳が言う「美」とは、美醜の対比のなかにあるものではない。美醜が分かれる前の美である。・・・柳にとって悲しみはいわば、超越へとまっすぐ続く道だった。》(243-244p)
そして、
《悲しみは、文化、時代を超え、未知なる他者が集うことができる叡知の緑野である》(245p)
1998年ニューデリーで開かれた国際児童図書評議会の世界大会にむけて皇后が出された『橋をかける』というメッセージが紹介される。この大会のテーマは「平和」だった。皇后は、新美南吉の『でんでん虫のかなしみ』のお話の記憶を語られる。「かなしみ」の殻を背負って生きることへの不安にかられるでんでん虫が、悲しみを持たない人は誰もいないことを知る。そして、「自分だけではないのだ。私は,私の悲しみをこらえていかなければならない。」と言って、もう嘆くのをやめるというお話。
皇后の言葉、
《その頃,私はまだ大きな悲しみというものを知りませんでした。だからでしょう。最後になげくのをやめた,と知った時,簡単にああよかった,と思いました。・・・この話は,その後何度となく,思いがけない時に私の記憶に甦って来ました。殻一杯になる程の悲しみということと,ある日突然そのことに気付き,もう生きていけないと思ったでんでん虫の不安とが,私の記憶に刻みこまれていたのでしょう。少し大きくなると,はじめて聞いた時のように,「ああよかった」だけでは済まされなくなりました。生きていくということは,楽なことではないのだという,何とはない不安を感じることもありました。それでも,私は,この話が決して嫌いではありませんでした。》(『橋をかける』)
この言葉を若松氏は自分に引きつけて言う。
《読書が、「悲しみ」との遭遇にはじまったことは決定的な出来事だった・・・ここに幼い少女における「読む」こととの出会いの萌芽がある。》(246p)
そして「力強い威圧ではない、涙もろい人情のみが此の世に平和を齎すのである」(『朝鮮の友に贈る書』)「悲しむとは共に悲しむ者がある時、ぬくもりを覚える。悲しむことは温めることである。悲しみを慰めるものはまた悲しみの情ではなかったか」(『南無阿弥陀仏』)との柳宗悦の言葉を援用しつつ、《悲しみの実相を語る真摯な言葉に出会ったとき、私たちの心はおのずと動き始める。真に「読む」ことが実現するとき、人はそこに描かれた悲しみによって、自らの悲しみを癒すことがある。》(250p)
私にはそこのところを読み通すのがつらかったのだが、原爆の原民喜、水俣の石牟礼道子についても書かれたこの本『生きる哲学』は、まさにその役割を果たしているのだろう。それをして「『読む』ことの秘儀」と言う。
《「読む」ということが真に営まれるとき人は、言葉を窓に彼方の世界を生きることになる。・・・「読む」とは不可視なコトバを感じることでもある。・・・それは字義通りの意味で生きることにほかならない。幼い魂にとってはいっそう「読む」ことの意味は大きい。彼らは、そこで自分以外の生があることを身をもって知ることになる。》(250-251p)
皇后の言葉、
《読書は私に,悲しみや喜びにつき,思い巡らす機会を与えてくれました。本の中には,さまざまな悲しみが描かれており,私が,自分以外の人がどれほどに深くものを感じ,どれだけ多く傷ついているかを気づかされたのは,本を読むことによってでした。
自分とは比較にならぬ多くの苦しみ,悲しみを経ている子供達の存在を思いますと,私は,自分の恵まれ,保護されていた子供時代に,なお悲しみはあったということを控えるべきかもしれません。しかしどのような生にも悲しみはあり,一人一人の子供の涙には,それなりの重さがあります。私が,自分の小さな悲しみの中で,本の中に喜びを見出せたことは恩恵でした。本の中で人生の悲しみを知ることは,自分の人生に幾ばくかの厚みを加え,他者への思いを深めますが,本の中で,過去現在の作家の創作の源となった喜びに触れることは,読む者に生きる喜びを与え,失意の時に生きようとする希望を取り戻させ,再び飛翔する翼をととのえさせます。悲しみの多いこの世を子供が生き続けるためには,悲しみに耐える心が養われると共に,喜びを敏感に感じとる心,又,喜びに向かって伸びようとする心が養われることが大切だと思います。》(「橋をかける」)
《悲しみは、誰かに受けとめられたとき、「愛(かな)しみ」へと姿を変える。・・・世には自分の知らないところで、あたかも自分の身代わりになって悲しみを生きている者がいることを教える。・・・悲しみの多いこの世を生きる幼子にとって、愛しみは、闇に隠れている喜びの場所を照らす光となる。愛しみには、魂を自ずと喜びへと導く働きがある。ここで皇后が語る喜びは、光と光に照らされるものが不可分であるように、けっして「愛しみ」と離れることがない。》(252p)との言葉で、皇后と若松との魂の響きあいのこの章は閉じられる。「読む」ことのありがたさを余韻が語ってくれている。そういえば先日こども園忘年会で、勤めて間もない若い職員に、「本を読め」と懸命に説く酔っ払った自分がいた。この本を読みおえたばかりだったのでした。
PR: ≪JAL国内線≫先得で早めの予約がおトク!
お前の番だ! 175
「でも世間じゃ、剣術は別としても、体術では親父さんの方が上だと評判だぜ」 「そんなのは、ワシの技の派手さに惑わされている素人の見損ないじゃな。剣術は云うまでもなく、体術の実力に於いてもワシは到底あにさんには叶わない」 「一度勝負してみると一目瞭然だけどな」 威治教士は満更冗談でもない口ぶりで云うのでありました。 「そうじゃ。確かに勝負すれば一目瞭然じゃ。だからワシはあにさんに今まで勝負を挑んだ事がない。勝負すればワシは屹度、手もなくあしらわれてお仕舞いじゃろうからな」 「そうかな? そうばかりとも思えないけど」 「ま、興堂派道場の門弟として、そう思っていてくれるのは有難いと云うものじゃがな」 興堂範士はここで花司馬筆頭教士に顔を向けるのでありました。「花司馬、お前はワシとあにさんが勝負したらどうなると思う?」 そういきなり嘴を向けられて花司馬筆頭教士は困惑の表情をするのでありました。 「いやあ、自分は是路総士先生も道分先生も、勝ち負けとか云う領域からは既に遠い境地に到られているのだと思っております」 「なんじゃ、有耶無耶を云って逃げおったな」 興堂範士は大笑するのでありました。別に花司馬筆頭教士に踏み絵させているわけではないので、それ以上彼の人を困らせる事は控えるようでありました。 「さて、あゆみちゃん」 興堂範士は話頭を変えるのでありました。「あゆみちゃんも、偶にはウチの道場に出稽古にお出でなさい。そうするとウチの女の門弟共が喜ぶ」 「確かにあゆみ先生は、ウチの女子の門下生達の憧れの的ですからね」 花司馬筆頭教士が肯うのでありました。「連中ときたら、自分の云いつけとか指導なんか聴きもしないくせに、あゆみ先生の云う事ならよく聴きますね」 「そりゃそうじゃ。ワシだって花司馬の云う事なんぞは聴く気もないが、あゆみちゃんの云う事だったら何でも素直に聴くわい」 興堂範士が雑ぜかえすのでありました。 「押忍。恐れ入ります」 花司馬筆頭教士は何となく真面目な顔つきで興堂範士にお辞儀するのでありました。その様子が可笑しかったのか、あゆみが口元を手で隠して笑うのでありました。 「じゃあ、あたし達はこの辺で失礼します」 あゆみが笑い収めて興堂範士に向かって頭を下げるのでありました。 「ああそうかい。何なら次の稽古にも出てその後飯でも食っていくかい?」 「有難うございます。でも今日は未だ総本部の方の内弟子稽古等もありますから、それに間にあうように帰りたいと思っておりますので」 「ああそういかい。稽古だと云うなら引き留めるわけにもいかんが」 「また近い内に、ゆっくりお邪魔させていただきます」 あゆみは少し後ろに躄って、興堂範士に向かって律義な座礼をするのでありました。 (続)
沖縄県民のオキテ
沖縄タイムスで記事が書かれていたり、広告が出ていたりして たくさん宣伝されていたので、読んでみました。 本当は立ち読みするとよかったのですが、新聞記事を読んだのが自宅だったので Kindle 版をダウンロードしてみました。罠にはまってるのか・・・? 著者の伊藤 麻由子さんは横浜生まれ。沖縄好きが高じて那覇で暮らし始め 縁あってウチナーンチュのりゅうくん(書家の書浪人 善隆さん)と結婚しました。 そんな中、彼女が「へー、ウチナーンチュって面白い」と感じたことをまとめたのが、この本です。 新聞記事を最初に読んだ時に思ったのが「この手の本って、まだ売れるのか」 だったのですが、この手の本って定期的に売れているんですかね? 昔からいろいろな人が似たような本を書いている気がします。 読んでみると「ウチナーンチュは雨が降っても傘は差さない」とか 「道路の追い越し車線の意味分かってんのか?」とか 「定食屋でお昼にみそ汁定食を食べている奴はたいてい二日酔い」とか なるほどその通り、沖縄で暮らす内地の人間であれば 1 度は感じたことがある 「沖縄あるある」がまとめられています。 瀬田 まいこさんのイラストがほわんとしていて、のんびり気分を味わえますが 正直この本がどうして新聞記事で紹介されたり、大きな広告で宣伝されるのか よく分からないです。 立ち読みできれば、それで満足ですよ。 さて仕事も無事に終わり、年末年始休暇を迎えることができました。 我が家は 2 年ぶりに義両親&姪と遊ぶ休暇になりそうです。 今年はどんな珍現象が起きているのか・・・ 性格の悪い私は、今からネタにするのを楽しみにしています。 皆様、良いお年をお迎えください。
☆マリーちゃんのしっぽ
童 話 『マリーちゃんのしっぽ』 (1) 作 元川 芹 香 「あっ、イグアナだ!」 庭の真ん中で、水遊びしていたなっちゃんが叫んだ。「ハッハッハ。それはイグアナじゃないよ。きっとカナヘビかな」 と、近くでバラの手入れをしていた、おじいさん。「ヘビじゃないよ!だって、足がちゃんとあったもん」 「しっぽがヘビみたいに長かっただろ。はじめて見た人が 『ヘビかな?』 って。それがひっくりかえって 『カナヘビ』 チョロチョロと動くから、チョロとも言うよ」 おじいさんは、なっちゃんのために、カナヘビをさがし始めた。「ふーん!カナヘビにチョロって、名前が二つもあるの?」 「そうさ。それは夏子になっちゃん、二つあるのと一緒だよ。ほら、いたぞ!」 おじいさんは、両手をふくらませて、そっとカナヘビをつつみこんだ。 「ねぇ見せて、見せて。うわぁかわいいね。なのにカナヘビなんてかわいそう。今日からあなたの名前は、マリーちゃん」 おじいさんの指の間から首を出したカナヘビは、つるっと逃げ出した。「じーじ、逃げちゃったじゃない。もっとお話したかったのに」 怒ったなっちゃんは、おじいさんの服をひっぱった。「お腹がすいて、家にでも帰ったんだろうよ」 「そっか!バイバイマリーちゃん、またあそぼうね」 「あぶない、あぶない。おじいさんなんかにつかまるとは。あの子が僕のことを、イグアナなんていうから、おかしすぎて動けなかったんだ」 けど、マリーってメスじゃないか?カナヘビが草かげで休んでいると、なっちゃんとおじいさんは、家の中へ入っていった。 <つづく> ---------- 「縺れた綾糸」は23日で完結しました。今日から1月2日まで、童話『 マリーちゃんのしっぽ 』 を4回連載します。
本「哀しみの雨」理想の恋ってこういうのかもしれないと思わせる作品
「哀しみの雨」著者 サンドラ・ブラウン
★★★★☆(個人評価 ★多めならおすすめ)
15歳の貧しい家の娘キャロラインが恋したのは町の有力者の息子リンク。
ところがリンクは他の女の子を妊娠させよその町に移っていった。
12年のときが過ぎ…キャロラインは30歳も年の離れたリンクの父親ロスコウの妻となっていた。
そしてロスコウが癌で幾ばくもないとわかった時リンクが町に戻ってきた。
いいわ~。なんつーか、すんなりいきそうでいかなそうな恋愛の描き方がイイ。
脇役もすんごい魅力的やしね。
まぁこの手のお話しはハッピーエンドってわかっているけど、そこに至る過程で他の人まで超幸せになるっちゅー心温まるそして読んだあとほっこりする一冊ですわ。
最初出会いがあって、途中ごちゃごちゃして、ラストはハッピーエンド。
周囲も本人も幸せ~っちゅーのが王道やね。
読んで後味悪いってことがないからハーレクインはいいわ。
まぁしかしタイトルだけ見ても何のこっちゃわからんよね…。
ハーレクインの問題点の一つはタイトルの付け方やな。
手に取りずらいタイトルやったりするから読まず嫌いを増やしてる気がする。
読んでみれば面白いんだけどな。

恋愛小説好きは恋愛に飢えてるにゃ…
【本過去記事】
☆本「貴婦人の条件」たぶん私は貴婦人にはなれない、あの時代に産まれていても…
☆美人写真家を襲う怪しい影!?ラブサスペンス小説「霧にひそむ影」
 ←ブログランキング参加中です。恋愛に飢えてる方も満足してる方もポチお願いいたします!
←ブログランキング参加中です。恋愛に飢えてる方も満足してる方もポチお願いいたします!
↓家庭用脱毛器ケノン!私と娘も使用中!↓

ビブリア古書堂の事件手帖6 [book]
 三上延/KADOKAWA/お薦め度 ★★★★
三上延/KADOKAWA/お薦め度 ★★★★
シリーズ第六弾
今回はまるごと一冊、「太宰治」。
太宰治の「晩年」を奪うため栞さんに重傷を負わせた男から奇妙な依頼が・・・違う「晩年」、太宰のかき込みのある、を捜して欲しい、と。
「晩年」の持ち主に警告、良からぬものが捜している、を発するため、依頼を引き受ける栞と大輔。
手掛かりは研究者と愛読者3人が集った「ロマネスクの会」、依頼者の祖父も参加者のひとり。そこで研究者の蔵書、「駈込み訴へ」、が盗まれていた。
ここから栞の祖父、愛読者3人がよく出入りしていた食堂のおばちゃん、大輔の祖母、研究者と親しかった古書店主らの不思議な繋がりが明らかになる。
祖父母たちの繋がり、孫たちの繋がり、過去と現在がシンクロする奇妙なめぐり合わせは何故!?
そろそろ完結編が近いようです。
偏見読書 2015年度版
life log 2014年
第四百三十五話_short 忘年薬
「さあ今夜は忘年会だ、みんな無礼講で楽しんでくれ」
部長のいつもの宣誓を皮切りに毎年行われる年忘れ飲み会がはじまった。ところがいちばん端の席で一人暗い表情で不味そうにビールを飲んでいる男がいた。暗木だ。
「おや、暗木さん、どうしました? 今日は嫌なことなどすっかり忘れて飲みましょうや」
すると暗木は泣き出しそうな顔で言った。
「俺はもうだめだ。今年は嫌なことが多すぎて、とても忘れることなんてできない」
弊社の産業医である俺は、こんなこともあろうかと持ち合わせていた飲み薬を鞄の中から取り出して暗木の手に渡した。
「暗木さん、これを飲んだら、一年間の嫌なことはすっかり忘れられますよ」
暗木は怪訝な顔で俺を見たが、躊躇することもなくその薬を口に含んでビールで流し込んだ。
「ど、どうです? 効いて来たでしょう?」
暗木の表情は相変わらずすぐれない。
「ええ、確かに今年のことはすっかり忘れることができたようです」
「じゃぁ、今夜は楽しく……」
「でも、ダメなんです」
「なにがダメなんです?」
「今年のことは忘れたが、前の年も一年間嫌なことばかりで……」
了
↓このアイコンをクリックしてくれると、とてもウレシイm(_ _)m