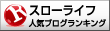『歩兵の本領』
著 者:浅田次郎
新 書:328頁
出版社:講談社
発行日:2004/04/15
たまに頭がショートしそうな時があるのですが、そういう時は適当に小説なんかを読んでいると大抵やり過ごすことができます。
ランニングするのも良いのですが、ストレスがたまった状態で走るとかなりの確立でオーバーペースになり、ひざなりを痛める結果に…
というわけで、今回は小説を読むことにしました。
こういう時に読む小説は、今まで読んだことのある作家の著作を選びます。
理由は単純。
気晴らしに読みたいのに、それがハズレだとさらに頭がヽ(`⌒´)ノするからです。
あとは、通勤電車の車内や駅の待合室で読むことが多いので、ハードカバーではなく持ち運びに便利な文庫本を選びます。
で、今回選んだのは浅田次郎
浅田氏は日本ペンクラブの会長も務めていて、最近も「日本ペンクラブ声明【太平洋戦争開戦の日に当たって】」を発表し、政府の政策を痛烈に批判
ある意味過保護に育てられた二世・三世議員とは異なり、自衛隊出身者である浅田氏の軍隊に対する考えは、歴史を直視するがゆえに優れた現実感覚を持つように思われます。
その浅田氏の陸上自衛隊時代の体験を元に書かれたのが『歩兵の本領』
舞台は1970年頃の市ヶ谷
世は高度経済成長を謳歌し、また学生運動も盛んな時期
こんな時代に自衛隊に集まったのは「どの顔も若いなりに人生を感じさせる苦労人の表情で、地連のオッサンに騙されたか、せっぱ詰まって転がりこんできた連中」
※地連:かつての自衛隊地方連絡部。現在は自衛隊地方協力本部。自衛官の募集等を行う。
給料は安く、世間から白い目で見られ、本質は軍隊なのに「軍隊」ではないとされた矛盾だらけの存在。
それが当時の自衛隊。
上官は、陸軍士官学校出身者や関東軍下士官ほか帝国軍人が多数で、陰湿な慣習はそのまま。
それどころか、集まってくる隊員自体が「おしなべてろくでなしの荒くれ者」が多いありさまで、隊内生活は旧軍に勝るとも劣らない。
昔読んだ安部譲二の『塀の中の懲りない面々』を髣髴させる雰囲気
しかし、旧軍と異なるのは戦争が彼岸のもので、「憲法があるかぎり、ベトナムに派兵される心配もない」こと。
その存在意義を認めてもらえるよう災害出動に精を出しても、基本的に肩身の狭い存在でしかなく、「過激派」を警戒して制服での外出も不可能。
また、旧軍出身者にも「自衛隊ハ戦ヲシナイ。攻撃サレタトキダケ防御スル。」という姿勢がある程度あったようです。
全編を読んでみて感じるのは、矛盾した存在ゆえの卑屈もあるでしょうが、市民や政治に対する自衛隊員の謙虚さです。
確かに、クーデターを想定した三矢研究(発覚は1965年)に露呈したように、統合幕僚会議レベルでは戦争は現実のものであったかもしれません。
しかし、そのような軍のおごりのようなものは、上層部に留まっていたのではないでしょうか。
また、その上層部にしても敗戦から四半世紀しか経過していない1970年頃は、戦争に対する現実感覚が今よりはあったように思われます。
では、翻って現在はどうでしょう?
ありえないと思われていた海外派兵が常態化し、災害出動に対する警戒心もほぼ一掃され、防衛庁は省に昇格。
そして9条改憲を公言する政権が誕生
旧軍的体質の復活ににらみを利かせていた旧内務省系の勢力も、とうの昔にいなくなってしまいました。
個人的には、第二のゴーストップ事件(比喩的意味で)が近い将来に起きるのではないかと危惧しています。
※ゴーストップ事件:1933年に発生した軍の台頭を象徴する事件
おまけ:「歩兵の本領」とは1911年に発表された日本の軍歌のタイトルでもあるらしい。「聞け万国の労働者」が、これの替え歌であるとのこと。左右が同じメロディーを愛好していたのですね♪